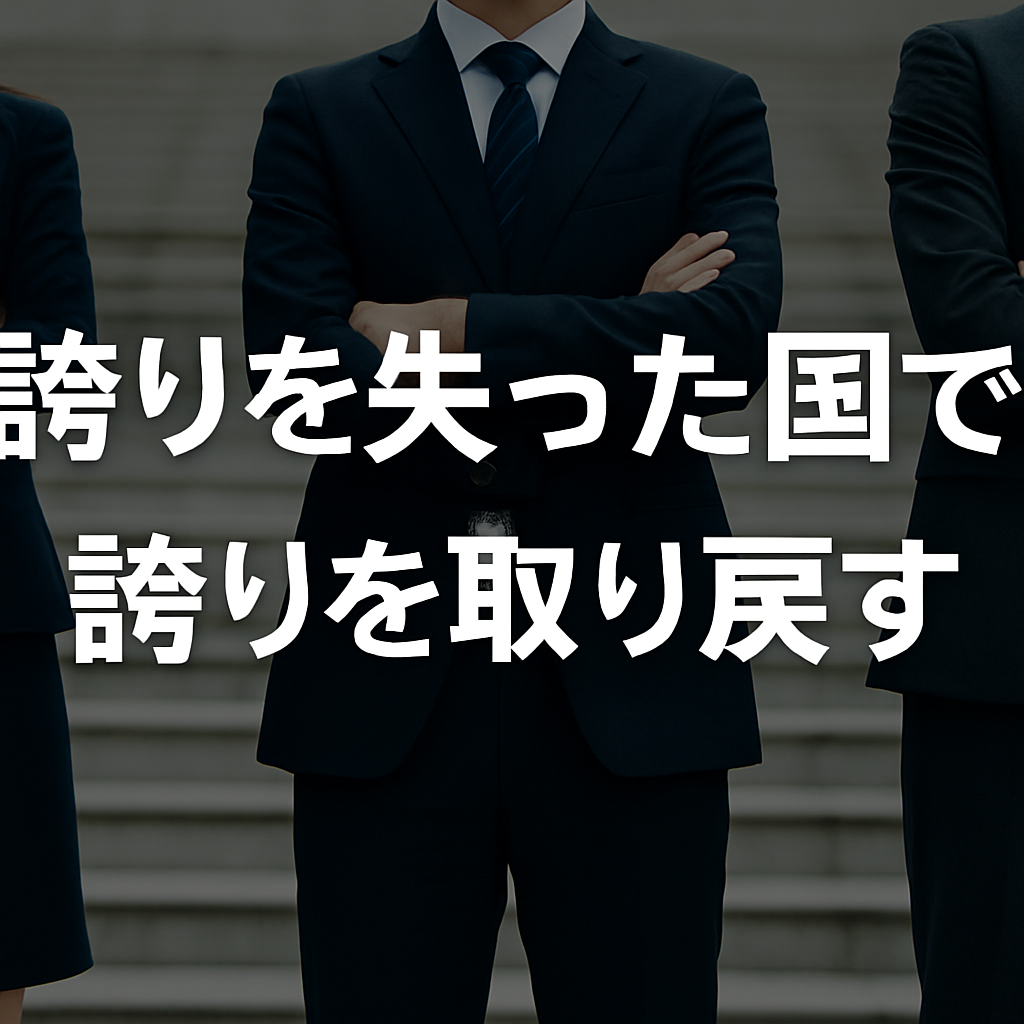プライドという言葉が、軽くなった。
人々はそれを、見栄や虚勢、あるいは傷つきやすい自尊心のことだと勘違いしている。
しかし本来のプライドとは、他人に誇示するための飾りではなく、自分自身を裏切らないための指針である。
その指針を見失った国は、やがて静かに、しかし確実に崩れていく。
今の日本が、その坂道を転がり始めているように見える。
一 誇りの変質
かつて日本人の「誇り」とは、他者の評価ではなく、自らの行いに恥じないことにあった。
モノづくりにおいても、教育においても、そこには「丁寧であること」「正直であること」「手を抜かないこと」という倫理があった。
しかし、経済成長が価値の中心に置かれるようになって以降、それらの倫理は効率の名のもとに軽視され、成果主義が誇りを「競争の結果」として扱うようになった。
この国の多くの大人が、誇りを数字で測るようになったとき、人間としての深さは静かに失われた。
数字を追って、心を失う。
「成功」と「誇り」が同義ではないことを忘れたとき、人はどれほど立派な地位にあっても、内面では崩壊している。
他人を押しのけ、嘘をつき、責任を他人に転嫁しながらも、自らの行為に疑問を持たなくなった。
そこにはもう誇りはない。あるのは「体裁」と「保身」だけである。みっともない大人だらけになる。
二 誤りを受け止められない大人たち
誇りを持つとは、誤りを認める勇気を持つことでもある。
だが、今の大人たちはそれを恥と捉える。
指摘されれば逆上し、正論を感情でねじ伏せ、己の小さな自尊を守るために真実を捻じ曲げる。
その姿を見て育つ若者たちは、「間違えたら終わり」「失敗は恥だ」と学んでしまう。
誇りとは、間違えないことではなく、間違えたあとにどう立ち直るかに宿る。
人は誤る。だが、その誤りを直視し、もう一度立ち上がる姿にこそ人間の尊厳はある。
それを放棄した社会では、学びも成長も生まれない。
そこに残るのは、責任を避け、他人を非難し、自らの正義に酔うだけの群れである。
ZIKUUでは、早く失敗をしようと声掛けしている。失敗が許される、そしてそこから正解を目指して努力する、それが認められていることをわかってもらうためだ。
失敗して一番辛いのは、失敗した本人だ。誰かに言われなくても本人が失敗したこと、自分の足りなさや不甲斐なさに怒りに似た感情を持つ。これが恥の感覚だ。だから、私は、失敗するのを眺めて、軽く肩を叩くというやり方が本人のためだと思っている。
三 教育と労働の中で失われた誇り
教育は、誇りを教える場であるべきだ。
だが現実には、従順と沈黙を教える場となった。
子どもたちは「答えを合わせる技術」を訓練され、「考える力」や「自分の筋を通す覚悟」を学ばない。
間違えることを恐れるようになった時点で、誇りの芽は摘まれている。
労働の場もまた、誇りをすり減らす構造を持つ。
誠実な人ほど疲弊し、声の大きい者ほど得をする仕組みが常態化している。
そこでは、信念を曲げない者が「扱いにくい」とされ、組織への忠誠が、誇りよりも上位に置かれる。
この国の労働文化が人の尊厳を奪い続けてきたことに、そろそろ気づくべきだ。
四 本来の誇りとは何か
誇りとは、他人に示すための姿勢ではなく、見ている者がいなくても正しくあろうとする意志である。「お天道さまが見ている」というあの感覚だ。
それは静かで、目立たず、報われないことも多い。
だが、誰かに見せるためでなく、「自分はこうありたい」と思える基準を守ること。
それが誇りであり、人間を人間たらしめる根っこだ。
誇りは努力の積み重ねの中に宿る。
自分の手で何かを築き、誰かの役に立ち、他人の痛みに鈍感にならないこと。
それは一朝一夕に身につくものではないが、それを手放した国は、どれほど富を築いても空っぽの国になる。
五 次の世代へ
今の日本の大人たちは、残念ながらもう立て直せないだろう。
便利さに慣れ、他人の言葉を疑い、自分の頭で考えることを放棄した者たちだ。
だが、まだ希望はある。
若い世代には、感性が残っている。
「違和感」を感じ取れる心が、まだ生きている。
もしその違和感を覚えたなら、どうか鈍らせずに育ててほしい。
正しいことを正しいと信じる勇気を失わないでほしい。
誇りとは、他人から与えられるものではない。
それは、自分の中に一本の筋を通すことでしか得られない。
金ではなく、信頼を選び、肩書ではなく、責任を果たし、損得ではなく、誠実を選ぶ。
その選択の積み重ねが、やがてこの国を静かに変えていく。
誇りを失った国で、誇りを取り戻す。
その仕事は、次の世代の手に託されている。
そしてその火を消さないために、私たちはせめて、沈黙の中で恥じることを覚えていたい。