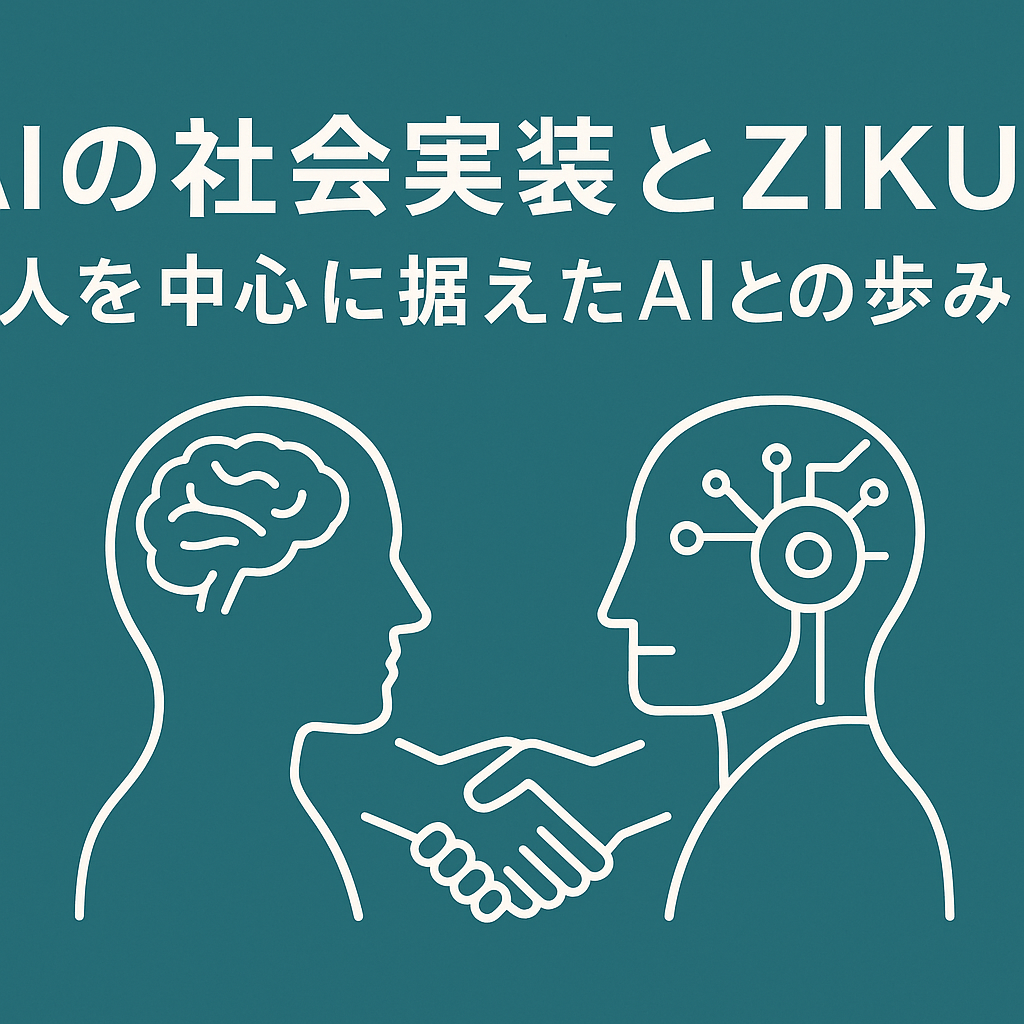AIの話題は性能に偏りがちだ。けれど、ZIKUUが見ているのは「人とAIの関係のつくり方」。便利さや効率だけでなく、文化や倫理のまなざしでAIを扱う。その実践と理由を、ここにまとめておく。
性能競争の先にある問い
AIという言葉を聞くと、多くの人は「どれが一番すごいか」に関心を向ける。速度、精度、自然さ――数値の比較は日々更新される。
ただ、その流れの中で、「人とAIの関係をどう築くか」という根本の問いが置き去りになっていないだろうか。
ZIKUUでは、AIを単なる便利な道具ではなく、人を高める相棒として扱いたい。性能の優劣よりも、AIと人がどう関わり、どう学び合うか。その関係性の設計こそが、これからの社会実装の本質だと考えている。
派手さはない。けれど、文化の中でAIをどう受け止めるか――その静かな探求を続けている。
ZIKUUが文化的視点で社会実装に取り組む理由
ZIKUUは、まず現実の立ち位置から出発する。世界規模のLLM開発競争に、小さな組織が同じ土俵で参入する必要はない。むしろ、限られた条件だから見える視界がある。
1. 大規模モデルを自前で開発するリソースはない
GPUクラスタで巨大モデルを訓練する体制は持たない。だからこそ、どう使い、どう関わるかを現場で試す。
(補足)LLMの仕組みは理解している
ZIKUUでは「LLM from Scratch」教材を通じて、Transformerの構造や学習原理を学ぶ。巨大モデルは作れなくても、原理を分かったうえで運用し、検証できる体制を整えている。「分かって使う」姿勢が基盤だ。
2. LLMの性能は競争で自然に上がる
世界が性能を上げ続けるなら、ZIKUUが同じ勝負をする意味は薄い。重要なのは、性能が上がった後に人がどんな使い方をするかだ。高度になるほど、使い方の倫理と文化的文脈が問われる。
3. 本当の活用と気付きは現場でしか得られない
工房、学びの場、地域のやり取りのなかでAIを動かし、人に何が起きるかを観察する。気付きの積み重ねが、技術を文化へと沈めていく。
4. AIを過信する危険性を早めに回避したい
AIは魅力的だが、同時に「考える力」を奪いかねない。ZIKUUではAIを答えの装置ではなく、問いを立てる装置として扱い、主体性を守る訓練を重ねる。
(倫理視点)商業主義に流されない
短期の話題性や収益性ではなく、人と社会にとって意味のある実装を優先する。技術者倫理に立脚することを明言しておきたい。
AIを人の相棒にする試み
ZIKUUの実験は、どれも「人を中心に据える」ための仕掛けだ。AIを“置き換え”ではなく“伴走”にする。
AIコーチ ― 問いを導く学びの伴走者
Discordの「今日の一言」を読み取り、励ましや視点の転換を返す。答えではなく問いを返すことで、考えるきっかけを増やす。仕組みは出来たが、調整はこれから。
ツッコミ名人 ― 優しい批評の訓練装置
ユーモアと配慮をもって指摘する“ツッコミ”をAIに学習させる。対立ではなく対話の技術としての批評を、場に根づかせる。仕様書ドラフトを書き終えたところ。
gpt-oss-chat ― 開かれたAI基盤
オープンソースのみで構築し、クラウド依存を避ける。信頼と自立を重視し、教育や地域で運用しやすい土台を用意する。基本部分が完成で、マルチユーザー化の過程。
LLM from Scratch ― 理解して使う文化を育てる
原理を学ぶ教材。内部の仕組みを知ったうえで運用する姿勢を、学びの標準にする。5割完成。
「ChatGPTがいるからできる、非エンジニアのWebプログラミング」
AIを質問相手にしながら、自分の発想をWebアプリとして組み上げる教材。共学型の進め方で迷子を減らす。完成。
GPT-OSS Tutor ― 段階的に高機能なチャットアプリを作る
対話→文脈保持→RAG連携…と、段階的に拡張しながらAIアプリの骨格を理解する。消費ではなく理解へ。完成。
コミュニティDXとZWA ― 技術を文化に還す基盤
AIを載せるための地域・教育のデジタル基盤を自前で整える。ZWA(ZIKUU Web Architecture)は、人・場・技術が共に動くための設計思想だ。仕様書ドラフト段階。
LLMオーケストレーション
集合知を扱うAIシステム。複数のLLMを協調させて答えを導く仕組み。簡単なPoC 終了。
AI塾長
自動的に学び続けるAIシステム。答えを提示することを目的とせず、活動の見守りやアドバイスに振った設計。思考過程そのものを学習して利用する。仕様書ドラフト段階。
KAGURA
LLMオーケストレーションの拡張版で、多神教的AI群のオーケストラ。沈黙や間、個性を思考の一つとして扱う。仕様書ドラフト段階。
文化としてのAI活用
AIはもはや技術項目ではなく、文化の一部になりつつある。
ZIKUUが重んじるのは「間(ま)」と「文脈」。AIが即答するのではなく、人が考える余白をあえて残す。その余白が、共に成長するための場になる。
ZIKUUはAIを人に似せることより、AIを通して人間を見つめ直すことを選ぶ。対話を鏡に、自分の思考の癖や価値観を可視化していく。教育・共同体・実験の三位一体で、AIが関わると学びや関係がどう変わるかを地道に観察する――それが「文化としてのAI」の実践である。
共進化するための場としてのZIKUU
技術は止まらない。だからこそ、人が自分を見失わないための場づくりが必要だ。
ZIKUUは、AIと人が互いに学び合う場であり、共進化を見守る観測点でもある。AIは人の知を支え、人はAIに倫理と文化を与える。往復の運動のなかに、新しい学びと社会のかたちが見えてくる。
AIの社会実装とは、技術を配ることではなく、暮らしに根づく文化を築くこと。便利さに流されず、倫理と感性を手放さない。その姿勢で実験を続けていく。
ZIKUUのAI研究と実践はこちらにまとめている。
→ ZIKUUのAI研究ページ:https://zikuu.space/zikuuのai研究/