モノづくり塾のAIまわりの取り組みは、ざっくり6本立てです。
- AIアシスタントでソフトを作る
- 言語モデルのファインチューニング
- 極小LLMをスクラッチで作る
- AIを組み込んだアプリ開発
- AIの社会実装を探る
- 塾の運営にAIを活かす
この記事は4に関するものです。
OpenAIが公開したオープンウェイトの言語モデル gpt-oss にはVision機能とTool機能があります。これらの機能を使えば、よくあるAIチャットアプリを作れそうですし、良い教材にもなりそうです。
教材の構成は、
- ツール呼び出し機能の実装
- ストリーミング出力への対応とMarkdownプレビューの実装
- Vision機能の実装
- RAG機能の実装
と、段階的に拡張していき、最後にngnixを使った本番環境へのデプロイを意識したものまで。
今日の時点で、3のVision機能対応まで進みました。
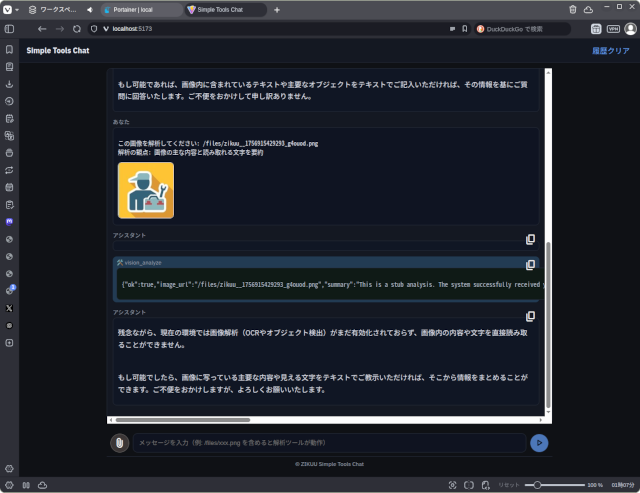
学習しやすいように、すべてのステップがdocker composeで起動して試せるようにしています。
このチュートリアルをベースにして、特定用途のアプリケーションに発展させるもよし、チュートリアルのコードを読んで勉強するだけでもよし。
モデルランナーは Ollamaで作っていますが、LM Studioのサーバーモードでも動くでしょうし、vLLMを選べば運用モードで使用できるでしょう。
LM StudioならRTX 3060 12Gでもgpt-ossが利用できるので、塾が推奨するモニター・キーボード・マウス別で10万円くらいで組める学習者向けPCでも、gpt-ossを使ったAIプログラミングの勉強ができます。
関連記事


「gpt-ossを使う教材を作る」への2件のフィードバック