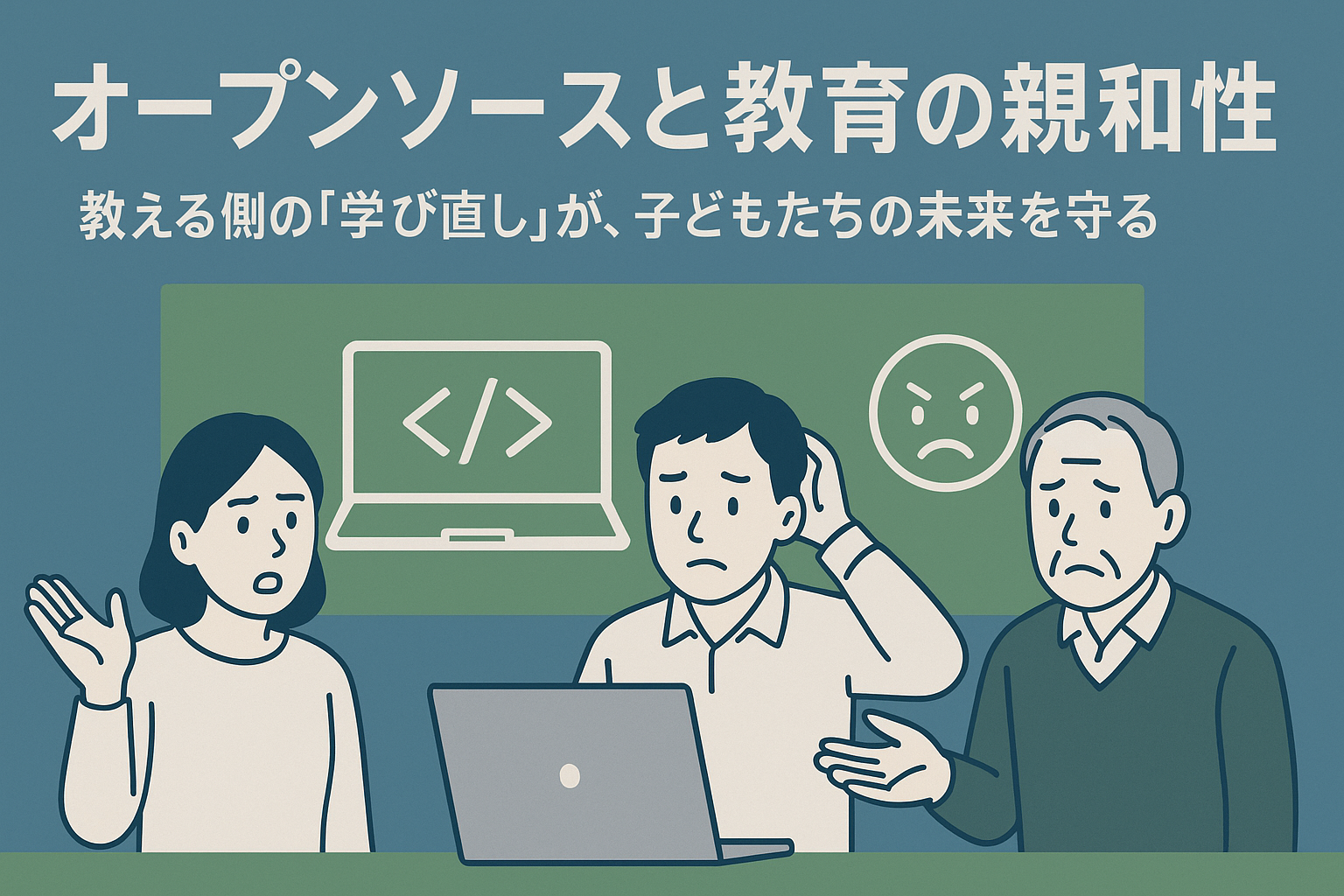オープンソースの精神は、理念ではなく実践の教育です。
子どもたちは、使い方よりも仕組みを学び、
与えられるよりも、自ら考え動く力を身につけます。
そこにこそ、教育の原点と本当の効果があります。
― 教える側の「学び直し」が、子どもたちの未来を育てる ―
ZIKUUでは、オープンソースの利用を積極的に推奨しています。
それは単なる費用削減の手段ではなく、教育的な実践として効果があるからです。
自由・共有・自立――この三つの精神は、まさに学びの根幹と重なります。
■ 教育現場に広がる「便利さの罠」
近年、多くの学校でChromebookやiPadを購入させる動きが進んでいます。家計の厳しい家庭には無視できない負担だと言われることもあります。私個人としては2万円程度購入できる中古ノートPCにオープンソースであるLinuxをインストールして使う方が良いと思っています。
デジタル教育の推進と聞こえは良いですが、実際には、教師側の知識不足がその背景にあります。
「安全そう」「管理しやすい」という理由だけで、特定企業の環境に依存する――
それは教育の名を借りた思考停止に他なりません。
機器の便利さが、子どもの探究心を奪う。
教育者が「なぜその道具を使うのか」を説明できないままでは、子どもたちに「なぜ学ぶのか」を教えることもできません。
■ 学びの構造を知ることが、思考を育てる
オープンソースの環境は、決して「楽」ではありません。
不具合もあれば、設定も自分で行う必要があります。
しかし、それこそが最も教育的なプロセスです。
子どもがネットで資料を読み、設定を試し、失敗から学ぶとき、
「思考力」「課題発見力」「協働的学び」が自然と身につきます。
つまり、実践を通じて育つ教育効果があるのです。
一方、閉じた環境ではその機会のほとんどが失われます。
決められた操作しかできない世界では、創意も責任も育ちません。
教育は「安全に使わせること」ではなく、「安全に探求させること」です。
■ 教師が学び直すとき、教育は蘇る
ZIKUUがオープンソースを推奨する最大の理由は、
教師自身が学び直せる環境であることです。
マニュアルに頼らず、ネット上の知恵や仲間とともに試行錯誤する。
このプロセスにこそ、教育者としての成長が宿ります。
「わからない」と言える教師が、子どもの「わからない」に寄り添える。
「試してみよう」と動ける教師が、子どもに挑戦する勇気を伝えられる。
そうした教育者の姿勢そのものが、子どもに模範としての学びの効果を生み出します。
子どもたちと一緒に歩んでいくという指導もあるんですよ。
■ 未来の教室へ
ZIKUUでは、多少の不便さを恐れません。
なぜなら、その不便さこそが、学びを深める装置だからです。
高価なサポートの代わりに、自分たちの知恵と協働の力があります。
それを通じて、子どもも教師も共に育ちます。
オープンソースは、理念ではなく実践の教育。
不便さの中にこそ、成長の芽が宿る。
大人が学び直すとき、教育は本当の意味で「生きた学び」へと変わります。